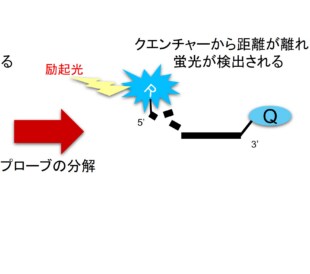前回に引き続き今回のテーマも「蛍光観察における漏れ込み」です。前回は、蛍光観察における漏れ込みについて概念的な説明をしました。今回は具体的な例を挙げつつ、より詳しく紹介していきます。
▼もくじ [非表示]
蛍光観察における漏れ込みの実例
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Phalloidinで染色したサンプルを弊社の蛍光顕微鏡Invitrogen™ EVOS™ M5000 Imaging Systemで撮影したものを例に見てみます。
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Dyeは最大励起波長581 nm、最大蛍光波長609 nmの蛍光色素で、Texas Red™フィルターでの観察が適している蛍光色素となります。

ところが、Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Dyeの観察に使用されるCy5®フィルターセットでもAlexa Fluor 594 Dyeはわずかですが励起され、蛍光を検出できてしまいます。

これはAlexa Fluor 594 DyeとAlexa Fluor 647 Dyeを同時に染色するとAlexa Fluor 647 Dyeを検出する際にAlexa Fluor 594 Dyeの蛍光も検出してしまっている可能性を示唆しています。
それではこの蛍光の漏れ込みを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか?
解決策1 使用する蛍光色素の波長を離す
有効な方法は、使用する蛍光色素同士の波長を離す方法です。前回のブログでご紹介したおすすめの蛍光色素の組み合わせであるInvitrogen™ Alexa Fluor™ 488 DyeとAlexa Fluor 594 Dyeで見てみましょう。Alexa Fluor 488 Dyeの蛍光波長スペクトルは、Alexa Fluor 594 Dyeの検出で使用するTexas Redフィルターセットでは励起されないことがわかります。よって励起波長に関してはわずかながら検出可能となっておりますが、励起自体されないためにAlexa Fluor 594 Dyeの観察の際に漏れ込まないことが分かります。

Alexa Fluor 594 Dyeの蛍光スペクトルも見てみましょう。Alexa Fluor 488 Dyeの検出で使用するGFPのフィルターセットではわずかに励起されているものの、蛍光を検出することができないために検出することができません。

このように使用する蛍光色素同士の波長を離すことで蛍光の漏れ込みを防ぐことができます。
解決策2 漏れ込む可能性のある蛍光色素は蛍光強度の小さいものにする
実験の都合上、漏れ込みが生じる可能性がある組み合わせを使用する場合、漏れ込む可能性のある蛍光色素は蛍光強度の小さいものにします。
2つの蛍光色素を検出する場合、2つの蛍光色素の波長が離れており、同程度の蛍光シグナルを示しているのであれば、漏れ込み量はわずかですので、蛍光の漏れ込みが気になることは少ないです。
一方で発現量や抗体の性能が異なるなどの理由により、蛍光シグナルの差が大きい場合、各蛍光の検出の際の露光時間が変わり、漏れ込みが生じるリスクが高まります。核染色試薬、細胞のトレーシングなどに使用されるCFSE、F-アクチンの染色に使用されるPhalloidin、ミトコンドリアの染色に使用されるInvitrogen™ MitoTracker™ Dyeなどは抗体よりも強いシグナルを示すので同時に使用する際には特に注意しましょう。
まとめ
蛍光の漏れ込みが生じてしまった場合、本来蛍光が発生していない領域で蛍光が観察されてしまい、データの解釈を間違ってしまう可能性があります。
多重染色を行う場合には、蛍光色素の波長、蛍光強度を意識して、使用する蛍光色素を選択しましょう。
合わせて、1色のみで染色を行ったコントロールサンプルを作成することで漏れ込みが生じているか判断することができますのでご参考になさってください。
ご自身で蛍光色素を選択される際には、当社が提供するウェブアプリに蛍光スペクトルビューアーがあります。
波形データを確認したい蛍光色素を選択すると、励起波長と蛍光波長がグラフ表示され、励起蛍光スペクトルと各種フィルターの適合性を簡単に比較することができます。ぜひご利用ください。
【無料公開中】Molecular Probes蛍光教室PDF版
Invitrogen™ Molecular Probes™ 蛍光教室では、蛍光タンパク質 (FP) を利用した細胞観察や FP 融合タンパク質のデザイン、またデザインしたタンパク質を細胞に導入するためのコツをご紹介しています。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。