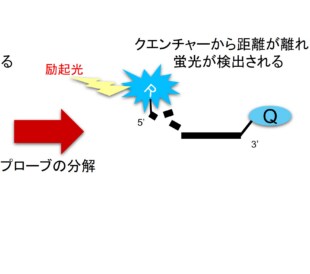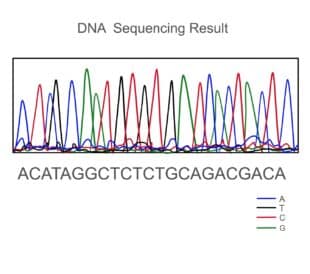これまでの記事で、酵素と収量や特異性、フィデリティとの関係、PCRの温度条件などについてご紹介してきました。今回は、「プライマーの設計」について述べたいと思います。
ここではプライマーの配列上での役割と設計の際に留意することを記します。
▼もくじ [非表示]
プライマー塩基配列の役割
20-25塩基程度で短い配列ですが、プライマー配列に無駄な部分はありません。プライマーの役割を大きく分けると2つの領域で異なる役割を担います。まずは3’末端側の約8塩基ですが、ここは酵素が結合して伸長反応をプロモートする領域と定義でき、最も特異性が要求されるところでもあります。プライマー設計では、3’末端側の約8塩基領域の塩基配列に特に注意を払う必要があります。
次に残りの5’末端側領域ですが、この領域はプライマー自身のTm値と特異性を高める領域と定義できます。長さを調整したりすることでプライマー全体としてのTm値を調整でき、またプライマー自身の特異性も高めることができます。このようにプライマー配列の中での役割分担があることを理解していただいたうえで、以下の留意点を読み進めていただければと思います。
プライマーセットの設計時に留意すること
プライマー同士のTm値を近似させる
前回にも記しましたが、2本のプライマーは固有のTm値をおのおのもち、Tm値はアニーリング頻度の指標となります。したがって2つのプライマーセットのTm値を近似させることは、各々のプライマーのPCR溶液中での動き(アニーリング確率とも言えます)をそろえることになります。一方のプライマーのみが活発に伸長したとしても、PCRの基本原理から考えると、十分な増幅が求められないことになります。そのためプライマーの挙動をできる限り同様に(Tm値をそろえるということ)は、効率的かつ特異性の高いPCR増幅につながります。
プライマー配列内での2次構造をさける
プライマーの設定位置は、増幅ターゲット領域により様々な制限等があることは、実際の研究過程においてしばしば起こります。また、2次構造に関しては、目で見ただけではなかなか予測がつきにくいのも事実です。それゆえ、専用ソフトウェアを使用して2次構造の可能性があるかどうかを事前に確認することをお勧めします。あまりに2次構造が予想される配列を設定せざるを得ないケースでは、アニーリング温度の検討・設定において、Tm値より数℃高く設定することで緩和されます。
4つの塩基をできるだけまんべんなく配列する
同じ塩基組成でも、配列の順番によってTm値は違ってきます。特にG(グアニン)とC(シトシン)の連続は、Tm値を急激に引き上げるだけでなく、テンプレートDNA中のCGクラスター等にもプライマーの一部分だけが、テンプレートDNAに強い親和性をもつことになります。
どうしてもCGクラスターをプライマー中にもたなければいけない場合は、5’末端側にCGクラスターを寄せるデザインをして、3’末端側にユニークな配列を位置づけるようにした方がプライマー設計パターンとしてはより良くなります。3’末端にGやCを設定するという工夫ももちろんですが、やはり重要なのは、目的とするPCR増幅を対象とする領域に対するプライマー配列の「ユニークさ」です。
ペアとなるプライマーセット配列を確認する
プライマー同士で相補的な配列をもつ場合、それらはPCR中に結合をして、PCR副産物(プライマーダイマー)を生成します。プライマーはPCRにおいて一番多い分子になりますので、当然有意にPCR産物として観察されてしまう結果となります。
プライマーダイマーは百害あって一利なしと言えます。その理由としては、PCR増幅中に基質であるdNTPsを大量に消費し、さらにポリメラーゼが本来のターゲットに働くことも妨げます。その結果、目的PCR産物の収量は減少する結果となります。またPCR産物を精製する場合も、このプライマーダイマーが40塩基近い産物であるために、目的PCR産物と分離するのが、難しくなるケースがよく起こります。
プライマーダイマーは、数100塩基レベルの非特異的PCR産物よりも非常に厄介な存在ですし、これはPCR条件を変更してもなかなか消失させることが難しいことから、事前にソフトウェアにより、この厄介なプライマーダイマーが生成するかどうかの確認を必ずしていただくことをお勧めします。
最後に
これまで3回にわたってPCRの最適化に関する情報をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?
前々回にも記載しましたが、PCRは机上でのデザインで、高い成功率を導くことのできる数少ない技術です。そして現在では、分子生物学での解析技術における必要不可欠な基礎的技術であると思います。ここで記したことだけでは、もちろんカバーできない特殊なPCR条件やテクニックもたくさんあるかと思いますが、この記事がみなさんの研究活動の一助になることを切に願います!
これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
他にも、PCRの基礎の復習や、より深い知識の獲得を目的とした無料PDFも提供しております!
▼主な内容
- PCRの基礎知識
- PCRのセットアップで考慮すべき6つの要素
- PCR反応条件における6 つの注意点
- DNAポリメラーゼの4つの主な特性
- 一般的な10のPCR法
- PCRを用いた7つのアプリケーション
- PCRに関するトラブルシューティングガイド
- 精製グレード選択のガイダンス
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。