前回のブログでは、総タンパク質定量法としてよく利用されている発色法(BCA法、Bradford法、
Lowry法、Pierce 660 nm法)についてご紹介しました。
これら発色法以外にも、総タンパク質定量法として、UV法や蛍光法があります。UV法は最も簡便な方法で、蛍光法は一般的に高い感度で定量が行える方法です。
では、なぜUV法が一番簡単なのに発色法がよく利用されているのでしょうか。また、感度が高い蛍光法にはどんなデメリットがあるのでしょうか?そして、総タンパク質の定量法にはこれだけさまざまな方法がありますが、結局どの方法が良いのでしょうか。
このブログでは、UV法や蛍光法の原理やメリットやデメリットのほか、総タンパク質定量法の
選び方についてご紹介します。
▼もくじ [非表示]
UV法:とにかく簡単
UV法は、名前のとおり、紫外波長である280 nmで吸光度を測定し、タンパク質を定量する方法です。

波長が280 nmなのは、タンパク質を構成するアミノ酸のうち、芳香族アミノ酸であるチロシンやトリプトファンなどに、この波長の光を吸収する性質があるからです。タンパク質は205 nm付近にもペプチド結合由来の吸収がありますが、205 nm付近は多くの物質が吸収を持つため、205 nmよりは吸収を持つ物質が少ない280 nmで実施されています。
原理
・芳香族アミノ酸が280 nmの波長を吸収する性質を利用
メリット
・サンプル溶液のまま測定できるため、とにかく簡単
・試薬などを購入する必要がなく、安価
・測定による活性低下がないため、測定後にサンプルを回収できる
デメリット
・タンパク質の種類によって芳香族アミノ酸の数が異なるため、吸光度が異なる
・感度が低い(50 μg~2 mg/mL程度)
・280 nmに吸収を持たないタンパク質(コラーゲン、ゼラチンなど)が存在する
・核酸やアミノ酸など、280 nmに吸収がある物質の吸光度も測定するため、
タンパク質は精製されているのが望ましい
UV法では、「吸光係数」を用いるLambert-Beerの法則からタンパク質濃度を計算します。

吸光係数はタンパク質によって異なり、例えばBSAでは約6.7です。光路長10 mmのセルを用いた場合、上の式にあてはめると、280 nmにおける吸光度が1.0のとき、BSAの濃度はc=1.0 / 6.7×10=約1.5 mg/mLになります。
BSAのようによく知られているタンパク質であれば、調べれば吸光係数はわかります。一方、吸光係数が不明なタンパク質も多く、さらにどんなタンパク質がどのくらい含まれているかわからないサンプルには、吸光係数をあてはめることができません。
しかし、複数含まれているサンプルだからこそ、小さい吸光係数のタンパク質も、大きい吸光係数のタンパク質も含まれていると言えます。よって、「280 nmにおける吸光度が1.0のときは1.0 mg/mLにしてしまう」ことで、ざっくりと総タンパク質の濃度を決めることができます。
なお、ここでもう1点注意しなければならないのは、280 nmの吸収を持っている物質はタンパク質だけではないということです。核酸やアミノ酸、ほかにも280 nmに吸収を持つ物質はあります。そのため、280 nmの吸光度が高いから「タンパク質がたくさん含まれている!」と思っても、実は見ていたのはタンパク質ではない別の物質だった、なんてこともあり得ます※。こういった点から、タンパク質定量法としてUV法よりも精度の高い発色法を選ばれることが多いのです。
※たとえば、A280/A260 <1.5 のときは核酸の混入が考えられるので、ほかの方法を検討しましょう。
しかし、これらのデメリットを差し引いてもUV法には大きなメリットがあります。それは、とにかく測定が簡単な点。何しろ、Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC微量分光光度計などの分光光度計でサンプルの280 nmの吸光度を測定するだけで定量ができるのです。試薬を購入する必要はなく、特別な手技もいりません。なお、NanoDrop One/Onec微量分光光度計であれば、Acclaro(アクラロ)という機能で、280 nmでタンパク質を測定したとき、核酸のコンタミネーションが予測される場合はアラートを出すこともできます。
さらに、この測定によってタンパク質の活性を損ねることは一般的にないので、測定後にサンプルを回収できます。たとえばクロマトグラフィーの装置と吸光度測定装置を連結させて、タンパク質の溶出のモニタリングしながら分取もできます。デメリットがありつつメリットも大きいので、サンプルやアプリケーションに応じてぜひ活用しましょう。
蛍光法:感度が高い

蛍光法は、蛍光色素や原理によってさまざまな特徴がありますが、一般的に、感度が高い定量法です。
感度が高いことは、わずかしかないサンプルでも定量ができるという大きなメリットを生みます。
原理
・蛍光試薬によってさまざま
メリット
・感度が高い
・研究室にある機器やサンプルに合わせて蛍光試薬を選ぶことができる
デメリット
・蛍光検出器やプレートリーダーが必要
・蛍光試薬や方法によっては、タンパク質の配列依存性がある
(第一級アミンに結合する蛍光試薬など)
蛍光法で定量するには、蛍光検出器やプレートリーダーが必要です。ひと昔前は高額な大型機器が多かったのですが、現在は持ち運びできるコンパクトなサイズの機器も多く出ています。そのため、この点はもはや「デメリット」ではないかもしれません。たとえば、代表的なコンパクト蛍光検出器としてInvitrogen™ Qubit™ 4 Fluorometerがあります。
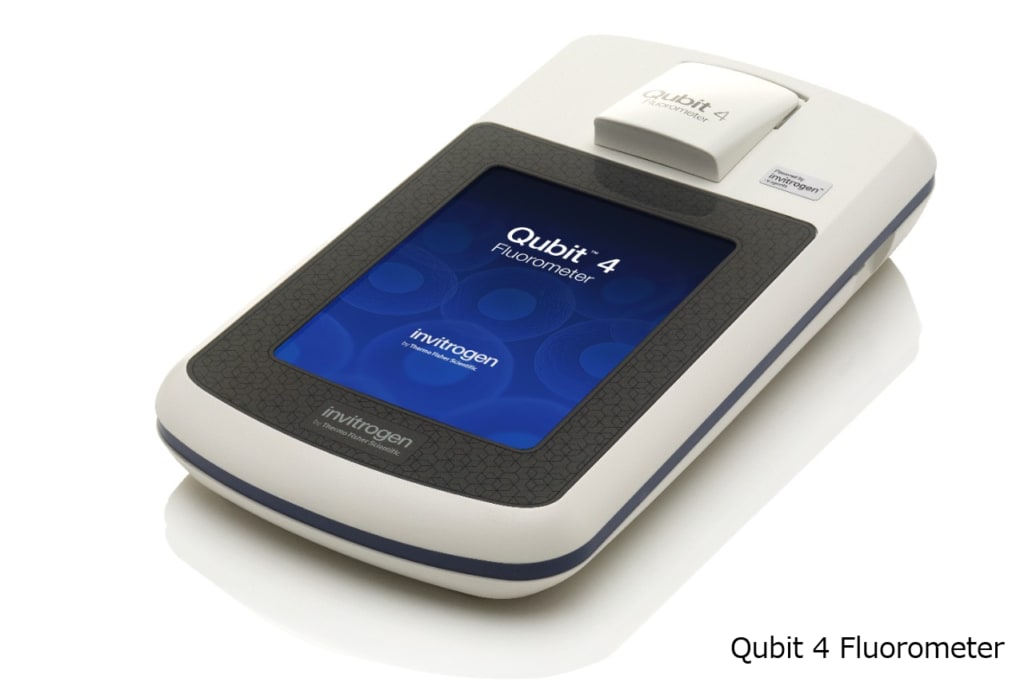
Qubit™ 4 Fluorometer は、タンパク質以外にもDNAやRNAを測定できる機器です。サイズはiPad™(iPad Air™)と同じくらいで、重さも1 kg未満。小型で軽量です。定量するときは、専用キットで作成したWorking Reagentを、スタンダードやサンプルと混ぜて測定するだけ。Qubit™ 4 Fluorometerが画面に濃度を表示してくれるので、どなたでも簡単にタンパク質の定量ができます。これのほかにも8連チューブで測定できるInvitrogen™ Qubit™ Flex Fluorometerもあります。
Qubit Fluorometer用のタンパク質定量キット:
Invitrogen™ Qubit™ Protein and Protein BR Assay Kits
・感度100 µg/mL ~ 20 mg/mL(製品番号A50668)
・感度12.5 µg/mL ~ 5 mg/mL(製品番号Q33211)
そのほかの蛍光を用いたタンパク質定量法として、界面活性剤を介して蛍光色素がタンパク質に結合するInvitrogen™ Quant-iT™ Protein AssayやNanoOrange™ Protein Quantification Assay、タンパク質のアミノ基に結合するInvitrogen™ CBQCA Protein Quantification Assay、バッファー成分の影響を受けにくいInvitrogen™ EZQ™ Protein Quantification Assayがあります。それぞれ励起波長や蛍光波長、蛍光色素の性質などが異なりますので、選択ガイドを利用して、お持ちの検出器やサンプルに合ったものを選びましょう。
結局、どの総タンパク質定量法がよいのか?
さて、数回にわたって総タンパク質定量法をご紹介してきましたが、選択肢がたくさんあって、結局どの総タンパク質定量法が良いのか迷ってしまいますよね。しかし、「どの総タンパク質定量法が良いのか」という問いに、答えはありません。総タンパク質定量法に「万能な方法」はないからです。それぞれメリットとデメリットがあるからこそ、1951年に開発されたLowry法を含め、複数の方法が今でも使われており、さらにメーカー独自の方法など新しい定量法も開発され続けています。万能な方法はないからこそ、原理やメリットとデメリットを見極めて、サンプルや下流のアプリケーションに適した総タンパク質定量法を選ぶことが大切です。
表. 総タンパク質定量法まとめ ※クリックで拡大表示できます。

「万能な総タンパク質定量法」はない。
サンプルやアプリケーションに合った定量法を!
総タンパク質定量法には、BCA法やBradford法などをはじめとした発色法、簡便なUV法、感度が高い蛍光法など、さまざまな方法があります。しかし、万能な定量法はありません。だからこそ、各定量法の特徴を捉えて、サンプルやアプリケーションに適した定量法を選択することが、迅速で精度高い定量を行う近道になります。
このブログを見た人は、こんなブログも見ています。
BCA法、Bradford法、Lowry法など、“総”タンパク質定量法の原理まとめ|知っておきたい!タンパク質実験あれこれ 第4回
“総“タンパク質定量法の種類をまとめてみた|知っておきたい!タンパク質実験あれこれ第3回
【無料ダウンロード】タンパク質解析ワークフローハンドブック
効率的なタンパク質抽出からウェスタンブロッティングの解析ツールまで、包括的にソリューションを紹介しております。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申込みください。
iPad and iPad Air are trademarks of Apple Inc.
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。



